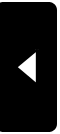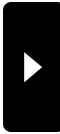2010年07月28日
涼感風穴~若木の風穴(かざあな)へ
武雄市若木町にあるミステリースポット!
若木の住民でも、行ったことがないという人もあり
地元のおじいさまたちは、さらに 奥まで行って遊んでいたというお話しもあり
昔は扉があって、貯蔵庫として使用されていたり
カイコを飼うのに使われていたとか
さまざまな言い伝えの残る若木の名所『風穴』

(写真はimakoko 武雄よかとこblogより)
さあ、今年も暑い夏となりました。
この暑さの中で行くからこそ効果のある場所です。
どうぞみなさん一緒に行ってみませんか?
ちょっと大変な山道もありますので、荷物はリュックで!
軍手、水筒、帽子など、しっかり準備してご参加下さい。
お申し込み先は まちおこしTAKEー0(テイクゼロ)江口さんまで!
 take_0_takeo(アットマーク)yahoo.co.jp
take_0_takeo(アットマーク)yahoo.co.jp 090-6636-9756(江口)
090-6636-9756(江口)保険加入のため、生年月日もご一緒におしらせくださいね!


まちあるきのあと、
NPO法人循環型たてもの研究塾
武雄三樹物語 2団体の活動発表があります。(ここまで参加費500円)
その後、場所を移して、交流会です!(参加費2500円)
飲んだり、食べたり、意見交換を楽しみましょう!
 なんと、当日は
なんと、当日は杜のうつわ 和樹(なごみのき)さん提供の県産木材のお皿を利用して
お食事をします!木の器の心地よさも体感できますよ!
お皿は・・・今から仕上げに入るそうです・・・できたてほやほやを使わせていただきますよ!
(お持ち帰りはできませんが、貸し出しはしてくださるそうです!)

2010年07月20日
ひっそりと森のようちえん
月に一回「森のようちえん」続いております
7月は17日に開催!の予定が、
参加の方がおらず、一緒にやっている方の子どもが熱を出し。。。
さすがに我が家のみで開催も寂しいので、
中止となりました
なので、「じゅんたて」の家創り塾と農の暮らしデザイン塾のお手伝いに。。。
息子がいては、お手伝いに程遠くなります(みなさまスミマセン)
が、息子は午前中の草むしりはテンション上がらずでしたが、
昼からの「えつり」は大喜びでした。

大人の手の先をじっと見ておりました。
少し手伝うこともできました。
家創り塾もかなり面白いですよ!
単発参加費2000円もしくは年会費2万円となりますが、
お試し参加(500円)もできます。
お子様連れの方は、森のようちえん同様に
「自分の子どもは自分でみる」となりますが、
とても素敵な体験ができます。
8月も森のようちえん行ないますので、
詳細決まりましたら、またこの場をお借りし、
お知らせさせていただきます

7月は17日に開催!の予定が、
参加の方がおらず、一緒にやっている方の子どもが熱を出し。。。
さすがに我が家のみで開催も寂しいので、
中止となりました

なので、「じゅんたて」の家創り塾と農の暮らしデザイン塾のお手伝いに。。。
息子がいては、お手伝いに程遠くなります(みなさまスミマセン)
が、息子は午前中の草むしりはテンション上がらずでしたが、
昼からの「えつり」は大喜びでした。
大人の手の先をじっと見ておりました。
少し手伝うこともできました。
家創り塾もかなり面白いですよ!
単発参加費2000円もしくは年会費2万円となりますが、
お試し参加(500円)もできます。
お子様連れの方は、森のようちえん同様に
「自分の子どもは自分でみる」となりますが、
とても素敵な体験ができます。
8月も森のようちえん行ないますので、
詳細決まりましたら、またこの場をお借りし、
お知らせさせていただきます

Posted by つちのや at
11:11
│Comments(2)
2010年06月22日
郷土史愛好会現地探訪・・・杉岳山大聖寺
若木町中山地区を通り抜けた場所に、杉岳山大聖寺(武雄市北方町)はある。
本堂の両脇には、巨大な木彫りの仁王像と金剛像。
本堂には不動明王が祀られている。 (九州36不動霊場めぐり 25番札所 )
和銅二年(709年)に行基が開山。赤いトタン屋根が目印であったが
開山1300年の、昨年2009年に本堂も瓦葺きに建て替わっている。

北方町から白石平野を見下ろす場所にあり、周囲には色とりどりの紫陽花が植えられている。
現在は多種多様な紫陽花があり、6月にはあじさいまつりとしてたくさんの観光客が訪れる。
●杉岳
本堂右手の山王社(御岳山)と書かれた石段を登ると、
杉岳と呼ばれるゆえんとなった杉の名残が見られる。
巨大な杉のうろのなかに、竹が生えていたというが、現在大きな杉の中に
お社が祀られている。

●マキの木
また境内には、日本一のマキの木と言われる樹齢500年とも1000年とも言われる
マキの木がある。

庫裡の入り口の板間には、大黒柱のように梁を支える巨大なマキの柱もある。
これは、たくさんのひとが祈祷に訪れ、なでさすっていたためか黒々と光っている。
柱には木肌そのままの美しさが見えるが、○に大の文字がいくつも焼き付けられている。
住職に尋ねると、さまざまな祈祷の際に、成就を願ってつけられたものだという。

●源為朝
この大聖寺は、鎮西八郎為朝(源為朝)が、黒髪山の大蛇退治を行う際に
(大蛇退治の物語については、川古の大楠為朝館のからくり人形をご覧いただきたい)
一週間こもって不動明王に祈願した寺であり、その御加護によって
無事に大蛇を討ち果たしたことを感謝し、
唐鐘信国作の明王の剣と大蛇の歯、大蛇の鱗を奉納したと言われている。
●名刀
その後、豊臣秀吉が朝鮮出兵前、名護屋城在陣に、九州各地から名刀を集めた際に
この明王の剣も取りあげられたが、その明王の剣だけが夜中に妖光を放つため
「これは世にも希な珍しき名刀なり」と添え書きを附して、この寺に返したとされる。
その後、戦時中にまた没収され、行方はわからない。
●大蛇の鱗
鱗については、ひとの頭の上に載せても余りあるほどの大きさだったというが
長崎の博覧会のおりに、貸し出したということだが、その後戦争が始まるなど
社会が混乱したこともあり、とうとう帰っては来なかった。
●大蛇の歯
最後に残る、大蛇の歯と言われるものは、今も大聖寺に残っている。
毎年8月の大祭には、公開されるとのこと。
●ふすま絵
一枚板のふすま板に生き生きと描かれたふすま絵も残されている。

その他、脇の山林にはモチの木と樫の木とがからみあった『夫婦円満の木(縁結びの木)』や

3本もの竹が幹から生えている大きな紅葉などもあり、
豊かな山林のなかに、異形の樹木の力を感じることもできる。

毎月奇数月に行われている郷土史愛好会。
今月はあじさいの見頃に合わせて変則となったが、よい現地探訪であった。
来月の郷土史愛好会は、中山地区から御所地区へ。
鎮西八郎為朝のおやしき(御所)、弓かけ松、薬水なども楽しみ♪

本堂の両脇には、巨大な木彫りの仁王像と金剛像。
本堂には不動明王が祀られている。 (九州36不動霊場めぐり 25番札所 )
和銅二年(709年)に行基が開山。赤いトタン屋根が目印であったが
開山1300年の、昨年2009年に本堂も瓦葺きに建て替わっている。

北方町から白石平野を見下ろす場所にあり、周囲には色とりどりの紫陽花が植えられている。
現在は多種多様な紫陽花があり、6月にはあじさいまつりとしてたくさんの観光客が訪れる。
●杉岳
本堂右手の山王社(御岳山)と書かれた石段を登ると、
杉岳と呼ばれるゆえんとなった杉の名残が見られる。
巨大な杉のうろのなかに、竹が生えていたというが、現在大きな杉の中に
お社が祀られている。

●マキの木
また境内には、日本一のマキの木と言われる樹齢500年とも1000年とも言われる
マキの木がある。

庫裡の入り口の板間には、大黒柱のように梁を支える巨大なマキの柱もある。
これは、たくさんのひとが祈祷に訪れ、なでさすっていたためか黒々と光っている。
柱には木肌そのままの美しさが見えるが、○に大の文字がいくつも焼き付けられている。
住職に尋ねると、さまざまな祈祷の際に、成就を願ってつけられたものだという。

●源為朝
この大聖寺は、鎮西八郎為朝(源為朝)が、黒髪山の大蛇退治を行う際に
(大蛇退治の物語については、川古の大楠為朝館のからくり人形をご覧いただきたい)
一週間こもって不動明王に祈願した寺であり、その御加護によって
無事に大蛇を討ち果たしたことを感謝し、
唐鐘信国作の明王の剣と大蛇の歯、大蛇の鱗を奉納したと言われている。
●名刀
その後、豊臣秀吉が朝鮮出兵前、名護屋城在陣に、九州各地から名刀を集めた際に
この明王の剣も取りあげられたが、その明王の剣だけが夜中に妖光を放つため
「これは世にも希な珍しき名刀なり」と添え書きを附して、この寺に返したとされる。
その後、戦時中にまた没収され、行方はわからない。
●大蛇の鱗
鱗については、ひとの頭の上に載せても余りあるほどの大きさだったというが
長崎の博覧会のおりに、貸し出したということだが、その後戦争が始まるなど
社会が混乱したこともあり、とうとう帰っては来なかった。
●大蛇の歯
最後に残る、大蛇の歯と言われるものは、今も大聖寺に残っている。
毎年8月の大祭には、公開されるとのこと。
●ふすま絵
一枚板のふすま板に生き生きと描かれたふすま絵も残されている。

その他、脇の山林にはモチの木と樫の木とがからみあった『夫婦円満の木(縁結びの木)』や

3本もの竹が幹から生えている大きな紅葉などもあり、
豊かな山林のなかに、異形の樹木の力を感じることもできる。

毎月奇数月に行われている郷土史愛好会。
今月はあじさいの見頃に合わせて変則となったが、よい現地探訪であった。
来月の郷土史愛好会は、中山地区から御所地区へ。
鎮西八郎為朝のおやしき(御所)、弓かけ松、薬水なども楽しみ♪

2010年06月21日
森のようちえん
若木でひっそり始めました。
くぬぎの杜からはじまる「森のようちえん」です。
自然育児に興味津々な若木と武内に転入してきた母ちゃん2人ではじまりました
自主野外保育のカタチをとっているので、
親子で参加して、みんなでワイワイやっています。
主な活動場所・・・武雄市若木町内(一緒に遊び場発見しましょう)
参加の対象は・・・就学前の子とその親(兄弟児いてもOKです)
時間は・・・月に一度、土曜日(9時半~13時半ぐらい
参加費・・・親子一組500円(兄弟児増えるごとに300円)保険代がかかります
興味のある方は、じゅんたてスズキまでメッセージください。
お待ちしています

第1回の様子。
みんなでお味噌汁をつくりました。
くぬぎの杜からはじまる「森のようちえん」です。
自然育児に興味津々な若木と武内に転入してきた母ちゃん2人ではじまりました

自主野外保育のカタチをとっているので、
親子で参加して、みんなでワイワイやっています。
主な活動場所・・・武雄市若木町内(一緒に遊び場発見しましょう)
参加の対象は・・・就学前の子とその親(兄弟児いてもOKです)
時間は・・・月に一度、土曜日(9時半~13時半ぐらい
参加費・・・親子一組500円(兄弟児増えるごとに300円)保険代がかかります
興味のある方は、じゅんたてスズキまでメッセージください。
お待ちしています

第1回の様子。
みんなでお味噌汁をつくりました。
Posted by つちのや at
10:28
│Comments(2)
2010年04月22日
大師山まつり
大師山まつり:大師山奉賛会原口清利さん
地区の皆さんでお餅つき
よもぎ餅はひとつひとつみんなでまるめます。

午前10時頃
担当の組の方々が、八十八の神仏に前掛けをかけていきます。

聖観音さんの一番さんのお堂にはお膳と白餅をお供えします。


午後1時過ぎ、次々とお参りの方がお越しになります。

午後2時半ごろ、奥の院の大師堂では、御詠歌があげられました。

雨がぱらつくときもありましたが
今年も無事に大師まつりが終了しました。
皆さんありがとうございました。
地区の皆さんでお餅つき
よもぎ餅はひとつひとつみんなでまるめます。

午前10時頃
担当の組の方々が、八十八の神仏に前掛けをかけていきます。

聖観音さんの一番さんのお堂にはお膳と白餅をお供えします。


午後1時過ぎ、次々とお参りの方がお越しになります。

午後2時半ごろ、奥の院の大師堂では、御詠歌があげられました。

雨がぱらつくときもありましたが
今年も無事に大師まつりが終了しました。
皆さんありがとうございました。
2010年04月20日
2010年04月16日
NEWSファイル佐賀18時10分~ ご覧下さい!
NHK佐賀・NEWSファイル佐賀18時10分~
のこしたいさがの木
『武雄市・川古の大楠』
川古の大楠と、その周辺ので暮らす地域の人々の姿を。
ちょこっと中継もあります。

のこしたいさがの木
『武雄市・川古の大楠』
川古の大楠と、その周辺ので暮らす地域の人々の姿を。
ちょこっと中継もあります。

2010年04月14日
よもぎを摘んで・・・大師山まつり21日
4月21日(水)は大師山まつり
毎年、大師山(通称:坊山)のある皿宿地区で
餅をつき、大師山でのまつりが行われています
この大師山には、様々な仏様観音様が八十八体まつられているのですが
実は、この大師山には
四国の八十八ヶ所と同じ形に、同じ神仏が配置されているのです。
つまり、その小さな山を一巡りすると、八十八ヶ所めぐりをしたのと
同じ御利益があるということ
今年も、近所のおばあちゃんが、何日もかけてヨモギを摘み
茹で、アクを抜き、この日のために準備をしています。

どうぞ、皆さんお越し下さい。
若木郵便局の交差点から東。登り口が見えますよ。
毎年、大師山(通称:坊山)のある皿宿地区で
餅をつき、大師山でのまつりが行われています
この大師山には、様々な仏様観音様が八十八体まつられているのですが
実は、この大師山には
四国の八十八ヶ所と同じ形に、同じ神仏が配置されているのです。
つまり、その小さな山を一巡りすると、八十八ヶ所めぐりをしたのと
同じ御利益があるということ
今年も、近所のおばあちゃんが、何日もかけてヨモギを摘み
茹で、アクを抜き、この日のために準備をしています。

どうぞ、皆さんお越し下さい。
若木郵便局の交差点から東。登り口が見えますよ。
2010年04月06日
縁側日記 第3回 原口清利さん
今回は皿宿・原口清利さんをお訪ねしました。
郷土史愛好会の会員でもあり、小学校5年生のしめ縄づくりでは15年前から指導をして下さっている原口さん。
昔のことを訪ねると、どんどんあふれるようにいろんなことをお話ししてくださいます。
神社での綱引きのこと、大楠の昔のようす。近所のお店のことなど
中でも大変興味深かったのは、『公徳箱』(こうとくばこ)のこと。
宿場町として栄えていた皿宿(昔は川古下宿であっただろうということ)では
往来が絶えず、夜遅くなることも多かったらしく、傘や提灯を備えた『公徳箱』というものが置かれていて、借りる人は名前を書いて借りて行き、また訪れたときに返すという、昔の助け合いの素晴らしいシステムだったようです。
ものを使い捨てる現代の世の中では考えもつかないですが、このような歴史を学ぶことで、ものの大切さ、助け合いの大切さも伝えていければということでした。
原口さんが、昔のことを勉強し始めたのが10年ほど前、郷土史愛好会(代表江越源一郎さん)が始まってからだったということで、学べば学ぶほど昔のことを知りたくなるということで、もっと早くから勉強を始めていればよかったとのこと。
若木にはたくさんの史跡があり、もう今では、『永野の風穴』のように歴史的によくわからないようなものもあるけれど、そういうものでも物語をつくって是非後世へ伝えていければ面白いと、とても楽しそうにお話しされていました。
原口さんは、77歳(喜寿)の時に皿宿のお祭りについての記録をまとめられ、88歳(米寿)の記念に大師山の地図を完成されました。
今年の大師山のお祭りでは参拝者全員に配布されて、大変喜ばれていたようです。
そして、90になる今年は、皿宿の昔の地図を書かれています。
これもまた地域の宝となることは間違いないです。
また、大楠公園の開設の際につくられたという大楠公園音頭は地元のことだからと、原口さんが作詞をされたということです。
振り付けなども町内の方につけてもらったという音頭ですが、今では耳にすることもありません。機会があるときにはぜひいろんなところでかけて欲しいものですね。
90になられるとは思われないほどの熱意溢れる様子で、話が尽きません。
これはぜひ地域の皆さんと共に学ぶ機会をたくさんつくっていきたいなあと思いました!
原口さんどうもありがとうございました!
■8月18日(火)には『川古の大楠いにしえトーク』が行われました。
この様子は『武雄三樹物語』さんで。
郷土史愛好会の会員でもあり、小学校5年生のしめ縄づくりでは15年前から指導をして下さっている原口さん。
昔のことを訪ねると、どんどんあふれるようにいろんなことをお話ししてくださいます。
神社での綱引きのこと、大楠の昔のようす。近所のお店のことなど
中でも大変興味深かったのは、『公徳箱』(こうとくばこ)のこと。
宿場町として栄えていた皿宿(昔は川古下宿であっただろうということ)では
往来が絶えず、夜遅くなることも多かったらしく、傘や提灯を備えた『公徳箱』というものが置かれていて、借りる人は名前を書いて借りて行き、また訪れたときに返すという、昔の助け合いの素晴らしいシステムだったようです。
ものを使い捨てる現代の世の中では考えもつかないですが、このような歴史を学ぶことで、ものの大切さ、助け合いの大切さも伝えていければということでした。
原口さんが、昔のことを勉強し始めたのが10年ほど前、郷土史愛好会(代表江越源一郎さん)が始まってからだったということで、学べば学ぶほど昔のことを知りたくなるということで、もっと早くから勉強を始めていればよかったとのこと。
若木にはたくさんの史跡があり、もう今では、『永野の風穴』のように歴史的によくわからないようなものもあるけれど、そういうものでも物語をつくって是非後世へ伝えていければ面白いと、とても楽しそうにお話しされていました。
原口さんは、77歳(喜寿)の時に皿宿のお祭りについての記録をまとめられ、88歳(米寿)の記念に大師山の地図を完成されました。
今年の大師山のお祭りでは参拝者全員に配布されて、大変喜ばれていたようです。
そして、90になる今年は、皿宿の昔の地図を書かれています。
これもまた地域の宝となることは間違いないです。
また、大楠公園の開設の際につくられたという大楠公園音頭は地元のことだからと、原口さんが作詞をされたということです。
振り付けなども町内の方につけてもらったという音頭ですが、今では耳にすることもありません。機会があるときにはぜひいろんなところでかけて欲しいものですね。
90になられるとは思われないほどの熱意溢れる様子で、話が尽きません。
これはぜひ地域の皆さんと共に学ぶ機会をたくさんつくっていきたいなあと思いました!
原口さんどうもありがとうございました!
■8月18日(火)には『川古の大楠いにしえトーク』が行われました。
この様子は『武雄三樹物語』さんで。
2010年04月04日
ジラカンス桜に出逢う
今年の初め、川内地区の名物として話題になったジラカンス桜。
桜が咲き始めると問い合わせも増え

地区のかたが看板を立てれて、道路から気づきやすくなりました。
今年4月5日ごろ満開に

ジラカンス桜は山桜
花と一緒に赤い葉っぱも出てきます。